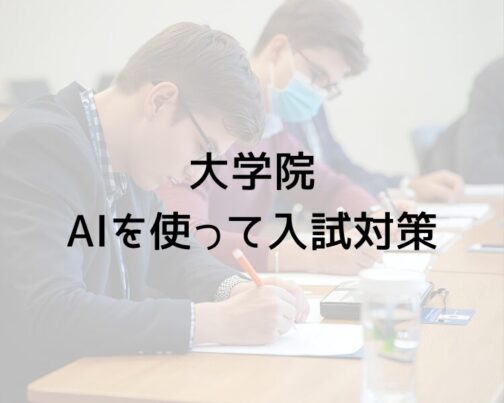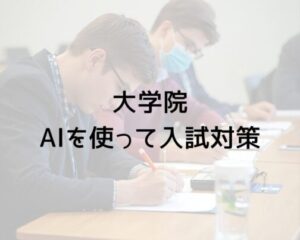社会人として放送大学大学院の入試に挑戦しました。
仕事や家庭と両立しながらの受験勉強は想像以上に大変でしたが、今回はAI(ChatGPT)を積極的に活用することで、限られた時間でも効率的に学習を進めることができました。
この記事では、実際にどのようにAIを使って試験対策を行ったのか、そして受験を終えて感じたことをまとめます。
 よしぶー
よしぶー悔いなくやれたと思います。
社会人の受験は「時間との戦い」
社会人にとって、大学院受験の一番の壁は勉強時間の確保です。
日中は仕事、夜は家事や家庭のこと。まとまった勉強時間を取るのは難しく、特に長文読解や論述対策は「どこから手をつければいいのか分からない」状態でした。
そこで取り入れたのが、ChatGPTによる効率的な学習法です。



仕事しながらほんとにしんどい!
ChatGPTを使った論述対策
論述問題は、過去の出題傾向や社会的テーマをもとに出題されることが多いと言われています。
ChatGPTでは、たとえば次のような使い方をしました。
過去の出題テーマを入力し、模擬問題を自動生成してもらう
自分で書いた答案を添削してもらう
800字程度の構成例(序論・本論・結論)を参考にする
これにより、「テーマに対してどう論理的に展開すればいいのか」が明確になり、短時間でも効率的に文章練習ができました。
特に、AIが示す構成パターンを繰り返し見ているうちに、自分でも自然と「型」が身についていく感覚がありました。
また、テーマになりそうな語句を深掘りしたく、その語句の要約を教えてもらうなどしていました。
例えば、「○○」とは?これについて書かれた800文字の論述模範解答を提示してなど・・・



実際だと何点くらいか採点してもらってました。
ChatGPTでの英語学習サポート
英語の長文読解は社会人受験生にとって大きな負担ですが、ChatGPTを使うことで勉強のハードルが下がりました。
分からない単語や文構造を簡潔に解説してもらう
英文をスラッシュリーディング形式で分解してもらう
要約や英文要約の練習を自動で出してもらう
特に要約練習では、AIが生成した模範回答と自分の答案を比べることで、「どの情報を残して、どこを削るべきか」がわかるようになりました。
辞書を引くよりもテンポよく理解が進み、限られた時間でも学習を継続できた点が大きなメリットです。



英語がほんと苦手で、逃げ続けたツケが回ってきました。
AI活用で感じた効果
今回の受験勉強で感じたAI活用の効果は、大きく分けて3つです。
時間短縮:調べ物にかける時間が圧倒的に減った
学習の継続性:短時間でも「一問一答」形式で気軽に復習できた
思考の整理:自分の考えを文章にまとめる訓練が自然にできた
特に社会人にとって、まとまった勉強時間が取れない中で“AIが常に隣にいる家庭教師のような存在”になるのは大きな強みでした。
一方で感じた課題
AIを使っても「自分で考える力」を完全に置き換えることはできません。
ChatGPTが生成した答案は整っているものの、「自分の言葉で書く」練習を怠ると、いざ試験本番では言葉が出てこないこともあります。
また、AIが示す情報が常に最新とは限らないため、自分で一次情報を確認する姿勢も大切だと感じました。
受験を終えて
受験を終えて感じたのは、社会人でもAIを使えば十分に大学院受験は可能だということです。
机に向かう時間が限られていても、スマホやパソコンで短時間に効率よくインプット・アウトプットを繰り返すことで、確実に力がついていきました。
特に放送大学のように社会人を対象とした大学院では、AIをうまく使うことが学習継続の鍵になると思います。
ChatGPTは、単なる情報ツールではなく、「一緒に考えるパートナー」として非常に心強い存在でした。
まとめ
AI(ChatGPT)を活用した受験対策は、
限られた時間でも効率的に学べる
自分のペースで復習や添削ができる
思考の整理や文章構成の練習に最適
という点で、社会人受験生にとって大きな支えになります。
今回の受験で「AI学習の有用性」を実感できたことは、合否に関係なく大きな収穫でした。
これから放送大学大学院を目指す方には、ぜひAIを味方につけた学習法を試してみてほしいと思います。