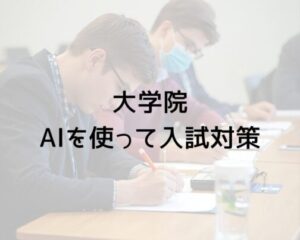近年、「葬式をしない」「お墓を持たない」という選択をする人が確実に増えています。
高齢化が進み、核家族化が進んだ今、従来の当たり前だった供養の形が大きく変わりつつあります。
「家族に迷惑をかけたくない」
「形式よりも、静かに自然に還りたい」
「お墓を守ってくれる人がいない」
そんな声が多く聞かれるようになり、今では「葬式もお墓もいらない」という考え方が、特別なものではなくなってきました。
その中でも、注目を集めているのが「シーセレモニー(海洋散骨)」という供養のかたちです。
この記事では、葬式をしない・墓を持たないという選択の背景から、シーセレモニーの流れ・費用・注意点までを、わかりやすく紹介していきます。
▼シーセレモニーの詳細を見てみる▼

「葬式をしない」という選択が増えている背景
以前は、誰かが亡くなれば親族や近所の人たちが集まり、盛大に葬儀を行うのが一般的でした。
しかし現在では、その形が急速に変化しています。
背景には、以下のような理由があります。
- 葬儀費用の高騰(平均100万円前後といわれる)
- 親族や地域のつながりが薄くなっている
- 遠方に住む家族を呼ぶのが難しい
- コロナ禍での小規模葬の定着
- 「自分らしい最期を迎えたい」という価値観の変化
「葬式をしない」といっても、まったく何もしないわけではありません。
火葬のみで見送る直葬(ちょくそう)や、ごく親しい人だけで行う家族葬など、形式を簡略化したお別れの形が主流になっています。
たとえば、葬儀場ではなく自宅でお別れをしたり、生前に本人が希望して「通夜や告別式は不要」と遺言を残すケースもあります。
つまり、「葬式をしない=冷たい」ということではなく、むしろ負担を減らし、心穏やかに送り出すための選択なのですよね。
「お墓を持たない」という選択肢が広がる理由
お墓もまた、昔のように「先祖代々の墓を守る」という文化が難しくなってきています。
都市部では土地代が高く、お墓を建てるには数百万円単位の費用がかかります。
さらに、維持費やお盆・お彼岸の帰省など、時間的・金銭的な負担も無視できません。
また、子どもがいない家庭や、家族が遠方にいる場合には「お墓を守る人がいない」という現実的な問題も。
その結果、最近では墓じまいを行い、遺骨を別の形で供養する人が急増しています。
墓じまいをするとなっても、またここからが大変だったりします。
そんな中で注目されているのが、自然葬(しぜんそう)と呼ばれる新しい供養方法です。
自然葬には、樹木葬や散骨(山・川・海などにまく方法)がありますが、その中でももっとも人気が高いのが「シーセレモニー(海洋散骨)」です。
▼シーセレモニーの詳細を見てみる▼

シーセレモニー(海洋散骨)とは?
シーセレモニーとは、遺骨を粉末状にして、専用の船で海に出て散骨を行う供養方法です。
「海に還る」「自然に還る」という発想から、宗教や宗派にとらわれずに行える点が特徴です。
日本では法律で散骨を禁止する規定はありませんが、モラルに配慮した方法で行う必要があります。
そのため、多くの人が専門業者に依頼して実施しています。
シーセレモニーの一般的な流れは次のとおりです。
- 遺骨を粉骨(パウダー状)に加工
- 花束や献酒などを準備
- 船で出航(30分〜1時間程度)
- 指定の海域で散骨
- 花びらや手紙を添えてお別れ
- 記念撮影や航海証明書の発行
散骨の際には、故人の好きだった音楽を流したり、静かに黙祷を捧げたりと、自由で温かな雰囲気の中で行われることが多いです。
シーセレモニーの種類と費用相場
シーセレモニーにはいくつかの形式があり、希望や予算に応じて選ぶことができます。概算です。
| 種類 | 内容 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 個別散骨 | 家族・親族のみで貸切船にて実施 | 約10万〜25万円 |
| 合同散骨 | 他の家族と同乗して行う | 約5万〜10万円 |
| 委託散骨(代行散骨) | 業者が代行して散骨を行う | 約3万〜7万円 |
| メモリアル航海付き | 海上でお別れ会を行うプラン | 約20万〜30万円 |
また、遺骨を一部だけ散骨して、残りを手元供養(ミニ骨壺やアクセサリーに納める)という人も増えています。
お墓を建てる場合に比べると、費用は圧倒的に安く、維持費も不要。
経済的にも、家族の負担が少ない方法といえます。
▼実際の費用を見てみる▼

シーセレモニーが選ばれる理由
なぜ今、シーセレモニーが注目されているのでしょうか。
そこには、金銭面だけでなく心の価値観の変化があります。
- 「海が好きだったから海に還りたい」
- 「自然の一部として眠りたい」
- 「家族にお墓の管理をさせたくない」
- 「静かに、けれど温かく見送ってほしい」
海はどこまでも広がり、誰かが訪れればそこが墓参りになる。
そんな考え方も増えています。
散骨の後に家族がその海辺を訪れ、花を手向けたり、空を見上げるだけでも心が落ち着く。
それがシーセレモニーのやさしさです。
シーセレモニーを行うときの注意点
法律上は散骨が禁止されていないとはいえ、自由にどこでも行えるわけではありません。
適切な手順やマナーを守ることが大切です。
- 遺骨は必ず粉末状(2mm以下)にする
- 海岸や港、釣り場など人が多い場所では散骨しない
- 許可を得た海域・業者を利用する
- 近隣住民や漁業関係者への配慮を忘れない
- 花は生花のみを使用(ビニールや金属製は不可)
こうしたルールを守ることで、トラブルを防ぎ、環境への影響も最小限にできます。
信頼できる業者を選ぶ際は、「散骨 口コミ」「海洋散骨 評判」などで検索し、公式サイトに実績・写真・証明書の発行があるか確認するのがポイントです。
▼シーセレモニーの内容を確認する▼

生前に準備する人も増えている
最近では、生前のうちに「自分の葬式や供養方法」を決めておく人も増えています。
終活ノートやエンディングノートに、「シーセレモニーを希望」と書き残すことで、家族の負担を減らすことができます。
また、生前予約をしておくと、費用を前払いしておけるため、残された家族が慌てずに済むというメリットもあります。
生前契約を行っている業者も多く、契約後はキャンセルや変更が可能なところも多いです。
シーセレモニー後の供養方法
散骨を行ったあと、「手を合わせる場所がなくなるのでは?」と不安になる方もいます。
しかし、シーセレモニーでは海そのものが供養の場になります。
例えば、
- 散骨ポイントを記した「航海証明書」を保管する
- 命日やお盆に、その海辺へ出向く
- 自宅に小さなメモリアルスペースを作る
といった方法で、心の中でつながり続けることができます。
墓石はなくても、想いを寄せる場所がある。それが現代の供養の形です。
自然に還るという生き方
シーセレモニーは、単なるお墓の代わりではありません。
それは、自然とともに生き、最後も自然に還るという人生の在り方そのものを映しています。
海は誰のものでもなく、すべてを包み込む存在。
その穏やかな青に抱かれて眠るというのは、どこか希望のある美しい選択ではないかなと考えます。
まとめ|葬式しない・墓もいらない、けれど心のこもった供養を
- 葬式やお墓を持たないという選択は、現代では一般的になりつつある
- 経済的負担を減らし、家族に迷惑をかけない終活の形
- シーセレモニー(海洋散骨)は自然に還るやさしい供養
- 法令やマナーを守り、信頼できる業者を選ぶことが大切
- 生前準備をすることで、家族にも安心を残せる
「葬式しない」「墓もいらない」という言葉には、冷たさよりも思いやりが込められています。
残された人への配慮、そして自然への感謝。
そんな優しい想いが詰まった新しい供養の形。それがシーセレモニーです。
これからの時代、誰もが自分らしく終えることを考えるとき、
その選択肢のひとつとして、静かに広がっていくことでしょう。
\価格が抑えられていて高評価の多いシーセレモニーはこちら/

散骨の他に遺骨ダイヤモンドという方法もありまして、別記事に仕組みや価格等をまとめています。
シーセレモニーのプランの中にもダイヤモンド葬がありましたので、こちらでも一度覗いてみると流れがわかります↓
シーセレモニーの遺骨ダイヤモンドプラン